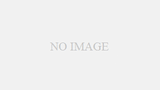ルネ・モーリス・ガットフォッセ、この名前あまり聞いたことがありませんね。実は、アロマテラピーという言葉を最初にこの世の中に送り出したのはこのルネさんなのです。この方はフランスの科学者・調香師だったそうです。
彼が、実験中に爆発を引き起こして、両手と頭皮にやけどを負ったとき、とっさにラベンダー精油をかけたところ、みるみる回復し驚いたというエピソードは有名。この経験から、彼は精油の治療的な効果に目覚め、植物の芳香成分「精油・エッセンシャルオイル」の研究に没頭することとなりました。
アロマテラピーという言葉は、ガットフォセが1928年に出版した”Aromatherapie”(芳香療法)という著書で初めて使われた。
では、アロマテラピーの歴史は1928年からなのかと思う方もいるかもしれませんが、そうではありません。学門的な系統的な研究が始められたというだけのことであって、アロマテラピーの歴史はもっとずっと長いものがあるのです。ざっと見渡したアルマテラピーの歴史は以下のようになります。古代エジプトまでその歴史は遡るようです。
概略アロマテラピーの歴史
| ●古代エジプト | |
| ●古代ギリシア | ヒポクラテス – テオフラストス – ヘレニズム |
| ●古代ローマ | 聖書 – ディオスコリデス – 皇帝ネロ – プリニウス – ガレノス |
| ●古代インド・中国 | アーユルヴェーダ – 神農本草経 |
| ●中世 | イブン・シーナ – 僧院医学 – サレルノ医科大学 – 十字軍 – ハンガリアン・ウォーター |
| ●16世紀~17世紀 | ジョン・ジェラード – ジョン・パーキンソン – ニコラス・カルペッパー |
| ●18世紀 | ケルンの水 – グラースの香水産業 |
| ●20世紀~ | ルネ・モーリス・ガットフォセ – ガッティー – カヨラ – ジャン・バルネ マルグリット・モーリー – シャーリー・プライス – ロバート・ティスランド パオロ・ロベスティ – 鳥居鎮夫 日本アロマテラピー協会 – 日本アロマ環境協会 |
多くの遺跡やパピルスに香油の存在が記録されています。これはアロマテラピーの原型とも言えるものでしょう。当時の医療やミイラ作製時の防腐剤、化粧品などとして広く利用されていたようです。
時代を重ねるにつれ、芳香精油は香水や化粧品へと利用が広がり、世界各地に香りの文化が築かれていくことになります。
19世紀になると、西洋医学や薬学がめざましい進歩を遂げるにつて、アロマテラピーに取って代わるようになります。衰退してしまうのです。こうした時代背景のもと、アロマテラピーという言葉が生まれます。これをきっかけに、多数の優秀な研究者がアロマテラピーの研究を開始するにつれて、芳香油の神秘的な効能を解く科学的アプローチによって、医療だけでなく、メンタルケアや美容の分野へとその活躍の場を広げていくこととなります。
近年になって、環境保護や自然回帰の声が高まりつつあります。植物生まれのピュアな香りを原点とするアロマテラピーは今後ますます注目されていくことでしょう。
日本のアロマテラピー
日本における香りの文化は、はるか昔の飛鳥時代に仏教の伝来とともに中国から伝えられた「香道」から始まったようです。はじめは、香木や練り香を炊き込む芳香浴が主流でした。はじめの頃は、仏教に儀式に使われたていたのですが、時を経て平安時代になると、香りそのものを楽しむことが主流になり、香りの優劣を競う「薫物合(たきものあわせ)」という遊びまで生まれてきます。恋人との逢瀬にロマンティックな香りを焚いたり、武将の兜に勇気づけの香りを移したりなど、生活の様々な場面で香りを利用していたようです。きっと、理屈ではなく生活上の体験から香りの持つ物心両面への有効性に気づいていたのかもしれませんね。
香道とは、一定の作法に基づいて香木をたき、その香りを鑑賞して楽しむ日本の伝統芸能です。茶道や華道と同時期の華やかな東山文化のもとに成立しました。現在、「御家流〔おいえりゅう〕」と「志野流〔しのりゅう〕」の二つの流派があります。
今から約1400年前の推古天皇の時代に一本の香木が漂着したのが日本で初めての香木の渡来です。
その後、仏教の伝来とともに香木は日本に伝わり、仏教儀式には欠かせないものとして、香木は発達しました。8世紀ごろ上流階級の貴族の間で自分の部屋や衣服、頭髪などに香をたきこめる「空薫物(そらだきもの)」の風習が生まれ、その流行に従って薫物合〔たきものあわせ〕という遊びが盛んになりました。二種類の薫物を調合して、その技術や匂いの優劣を競うものでした。そして、室町時代の華やかな東山文化の下で一定の作法やルールが作られ香道として完成しました。江戸時代に入り、香道は貴族だけのものではなく、一般の町民・庶民の間にも広まり香道は日本の伝統芸術として確立しました。